Presented by Suzume
illustration by 桃瀬 玲
illustration by 桃瀬 玲
朝食の後、腹ごなしをかねて望美は九郎に手合わせを願い出た。
怨霊との戦いの中で剣の腕は上達していたが、基本に忠実な日々の鍛錬も必要だからだ。
その点、九郎は同じ師を持つ兄弟子で面倒見も良いし、打って付けの人材だった。
野営の片付けを仲間たちに任せて、二人は立ち合いができる程度に広い場所を求めて歩を進めた。
「この先に河原があったな」
「そうなんですか?」
先を行く九郎が言うのに、望美はちょこんっと小首を傾げた。
「昨日水を汲みに行っただろう」
「私、そのとき白龍と薪を拾ってたから……」
「そうか。とにかく河原があるんだ。そこならばお前がどんなに大振りをしてきても遮るものがないから大丈夫だ」
からかうような物言いにムッとする。
確かに望美の太刀筋は九郎のものほど美しくはないかもしれないけれど、それを茶化されるのは面白くない。
望美は不機嫌な気分そのままに唇を尖らせて足早に九郎を追い抜いた。
「あ、おい、その辺りは滑るから気をつけろ」
「え? あっ、きゃぁっ!?」
九郎が注意を促したのと同時に望美はぬかるみに足を取られて、あっと言う間もなく見事に転倒してしまった。
数日前に降った雨でできた水たまりがまだ残っていたのだ。他の場所は陽光によって乾かされていたが、そこはちょうど繁った木々によって陽射しが遮られていたのだ。
「まったく、言っている側から……」
九郎が呆れたように呟くのを聞いて、望美の頭に一瞬で血が上る。
「そんなこと言ったって……痛っ!」
抗議するべく口を開いた望美だったが、立ち上がろうとした矢先に足首に走った痛みで思わず顔を顰めた。
転んだときに捻ってしまったのだろう。
立てないほどでも歩けないほどでもなさそうだが動かすと痛い。
しかしここで弱音を吐いたらこの兄弟子に何を言われるかわかったものではない。
生来の負けず嫌いも手伝って、望美は何事もなかったように立ち上がろうとした。
「待て、足を捻っただろう」
否定する間もなくしゃがみ込んだ九郎が望美の足首に触れる。
痛みよりも羞恥の方が先に立って、望美は座り込んだまま思わず飛びずさった。それによってすぐさま足に痛みが走り、また顔を顰める。
「望美?」
「い、いきなり何するんですか、九郎さんのエッチ!」
「えっち? あ、いや、誤解するな、断じてそういうつもりじゃない!!」
言葉の意味は解らなくとも望美が何を言いたいのかを察して、今度は九郎が狼狽えた。
「俺はただ、お前が足を捻ったんじゃないかと……」
「それはわかりますけど、いきなり女の子の足に触るなんて失礼じゃないですか!」
真っ赤になって言い訳をする九郎に望美がきっぱり言い放つ。それに対して、彼はぐっと詰まって顔を背けた。
気まずい沈黙が二人を包んだ。
本当のことを言えば、足に触れられるくらい、そんなに騒ぐほどのことじゃない。
これが将臣や譲だったら望美だってこんなに大袈裟に騒いだりしなかっただろう。
相手が九郎だから、こんなにも恥ずかしいのだ。
しかし当の望美はその理由を正しく理解するよりも、意地の方が先に立ってしまっていた。
望美が少し言いすぎたかなと思い始めた頃、九郎が、
「すまなかった」と小さく詫びた。
こういうときの九郎は決して言い訳をしない。
自分に非があると思ったとき、すぐに謝罪できることや素直に過ちを認めることができるのは彼の潔さの表れだ。
九郎のこういう性格が、周囲に良い人材が集まる所以なのかもしれない。
そう思ったら過剰反応してしまった自分が急に恥ずかしくなってきた。
望美は俯いたまま、
「こっちも大袈裟に騒いじゃってすみませんでした」と謝った。
九郎は赤い顔をしたまま頷くと、望美に背を向けてしゃがみ込んだ。
「ほら」
「え?」
「その足ではみんなの元に戻れないだろう。俺が連れていってやるからおぶされ」
彼はそう言って、むこうを向いたままで望美に促した。
確かにこの足では修行どころではないし、獣道を戻るのも難しい。
言い方はつっけんどんだが、九郎が自分を気遣ってくれているのが解って、望美はなんだかくすぐったい気分になった。
この兄弟子は口は悪いが面倒見はすこぶる良い男なのだ。そして照れているときほど口が悪くなるということも、この数ヶ月の間に学んでいた。
「それじゃお言葉に甘えて、九郎さんの背中、借りますね」
望美は九郎の肩に手をかけて立ち上がって、そのまま自分の身体を彼の背に預けた。
九郎はふわっと重さを感じさせない動きで立ち上がって、望美と自分の刀を持って今きた道を引き返した。
「重くないですか?」
黙っているのに耐えられなくなって、望美は先ほどから不安に思っていたことを尋ねた。
「大したことはない。望美、ちゃんと食事は摂っているんだろうな?」
「え? 食べてますよ?」
「それならばいいが……それにしては軽すぎるんじゃないか?」
「やだ、そんなことないですよ。朔なんかもっとスリムなのに出るとこは出てて……」
思わず口を突いて出た言葉にハッとして口を噤んだが時すでに遅しだ。
九郎の耳が赤く染まったのを見て恥ずかしさがいや増した。
「き、聞き流してください!」
兄弟子に負けず劣らず真っ赤になって言った望美だったが、
「そんなことはない」という九郎の言葉に目を瞬かせた。
彼が何を言いたいのか量りかねて、望美は続く言葉を待った。
「朔殿は確かに華奢だが、お前も充分に華奢だ。刀を振り回すには細すぎるほどだ」
「九郎さん……」
「それに……その……女らしい身体の丸みは、これからどんどん出てくるだろう。お前ほどの器量なら嫁の貰い手は引きも切らないだろうから心配することはない」
望美は自分の耳を疑った。
不器用で照れ屋な九郎から、まさかこんな言葉が聞けるだなんて思わなかった。
目の前にある彼の耳はますます赤みを帯びていて、この男がどれほどの恥ずかしさを伴って言ってくれたのかは一目瞭然だ。
そう思ったら先ほどちらっと胸を掠めたコンプレックスが途端に馬鹿馬鹿しく思えてきた。
「じゃあ、もしお嫁の貰い手が見つからなかったら、九郎さんが貰ってくれますか?」
望美は冗談めかして言ったが、その言葉には自分でも気づかない本音が織り込まれていた。
九郎はそれをどう受け取ったのか、小さく咳払いをして、
「まあ、仮とはいえ許婚だからな」と呟いた。
その言葉が嬉しくて、望美は顔を綻ばせて、
「約束ですよ」と念を押した。
二人の恋は、まだ始まったばかり。
色事に鈍い兄妹弟子の想いが形になるのは、あともう少し先の話である。
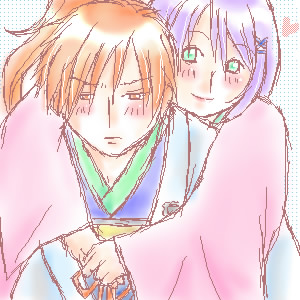
このお話は「最初に絵ありき」でした。
桃瀬さんからこのカットを見せてもらったSuzumeは、思わず、
「これにお話つけさせて下さい!」と志願したのです。
にもかかわらず、せっかくのラブラブなイラストだというのに恋愛途上の話になってしまい
情けないやら申し訳ないやら……(ほろり)
でも素直じゃない二人のやりとりは書いていて楽しかったです。